図書館フェス2015 講演「新しい図書館のはじめ方」講演内容全文
ページ番号 1025178 更新日 令和6年12月25日
2015年5月31日に開催した「東久留米市立図書館 図書館フェス2015」の一環として、
前塩尻市市立図書館館長・内野安彦氏の講演会「新しい図書館のはじめ方」を行いました。
以下はその記録です。
~内野安彦(うちの・やすひこ)氏プロフィール~
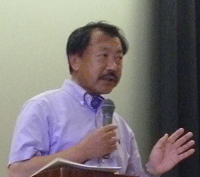
1956年茨城県生まれ。茨城県鹿嶋市立図書館長、長野県塩尻市立図書館長を経て、現在、常磐大学、同志社大学等の非常勤講師。
FMかしま「Dr.ルイスの“本”のひととき」のラジオパーソナリティーも務める。
〈著書〉
『だから図書館めぐりはやめられない』『塩尻の新図書館を創った人たち』(ほおずき書籍)『図書館はラビリンス』『図書館長論の試み』(樹村房)
※このページの講演内容は東久留米市立図書館が記録を作成し、講師に許諾を得て掲載しています。
無断転載・無断コピーはおやめください。
■水戸黄門は7人いるか
「茨城」と「テレビの歴史ドラマ」というこの二つで連想するとしたら、何かございますか?最近は数年やっていませんが、何回かやっているドラマです。
(参加者、挙手「水戸黄門」)
当たりです。さすが。さて、水戸黄門は何人いるか知ってます? これは実際にレファレンスがあったんです。正確に言えば博物館にですが、「水戸黄門は7人いると聞いたんですが、本当ですか?」
「そんな馬鹿な?」と、調べました。水戸黄門は7人いたんです。実は「水戸光圀は」と僕は聞いておりません。「水戸黄門は7人いたのか」というのが、茨城県立歴史館がレファレンスを受けたものです。
レファレンスというのは、図書館でいうところの「相談」です。ご来館された方が、悩んでいる。何か調べたいことがある。誰かに聞いたんでしょう、「水戸黄門は7人いるんだってよ」と。で、調べましたところ、「黄門」=「水戸黄門」、「黄門」=「中納言」、役職です。「黄門様」という役職名は、7人いた。それを、ちゃんと調べて、これを―今日もし「初めて聞いた」っていう方がいたらお得な情報です―「国立国会図書館」という所のホームページを見ていくと「レファレンス協同データベース」というのがあります。ここに、色々なキーワードを入れると、全国の学校図書館、公共図書館、大学図書館、専門図書館、色々な方々が、現場で受けたレファレンス、しかも大変時間のかかる回答まで、そういうものを自分のためだけにしないで、これを国立国会図書館に上げます。そうすると、国立国会図書館がインターネットで公開しています。ですから、「水戸黄門」「7人」と入れると、今の話が、ちゃんとデータベースに出ています。もしお疑いの方がいたら、こういう風にちゃんと出ております。(資料を回す)
■明日の図書館
これは『2005年の図書館像』と言われるものです(資料を示す)。15年前の平成12年に「5年後にはこんな風に図書館は、図書館ライフは、皆さんの生活は変わります。電子的にこれだけ発展します」と書かれたものです。もちろん、今となってみれば、相当のものが叶っています。やっぱり成長していると思います。でも、成長していないんじゃないかと思うものが一つあるんですよ。それが、僕は「明日の図書館」のためになるんじゃないかと思っています。
僕はラジオのパーソナリティをやっています。毎週月曜日、夜の7時30分、図書館のことばかり喋っている30分間の番組です。もう2年半続いています。全国から100人以上の図書館関係者、図書館学の先生、現職の図書館員、OB、ボランティアさん、さまざまな方に出ていただいています。出た方に、「全国のリスナーに一言メッセージを送ってください」というと、必ずこう言うんですよ。「一度来てくれませんか。一度来てくれると、分かりますから、図書館は。」そんな思いで、図書館員は日々やっています。
この今日のイベントもそうです。今日のイベントだって、日常のサービスだと足を運ばなかった方が、「面白そうだ」ということで来てくれている可能性もあります。
そして、今日のメインの話は「市民の皆さんと図書館のどういう関係ができればいいのか」。それがむしろ僕は、進化形の図書館の姿、「明日の図書館」だと思います。電子的な進歩もそうですが、基本部分は、市民の方と図書館の方がちゃんと「覚悟」をもってできれば、こんな素晴らしい図書館はないと思っています。ですから、図書館がどう変わるかではなく、図書館と利用者の関係がどう変わるか。たとえば、他県・他市町村から見たときに「東久留米はすごい」というのは、「図書館の本がいっぱいある」「施設がすごい」じゃなくて、「市民と図書館員の関係がすごい」という関係。僕はこれが最も進化的な図書館ではないかと思っています。
お配りしたレジュメ通りに、「図書館に大切なパートナー」ということで書かせていただきました。先ほど、図書館という世界の、国立国会図書館から他の館種も含めて全部つながっているというネットワークのお話をしました。
これは僕の母校でもあるんですけれども、『図書館情報大学の講演録・知の銀河系』という叢書が出ています。僕はこれが好きでしてね。帯についている言葉が好きで、短いので、ちょっとだけご紹介します。
“知りたいと思う欲求と知らせたいと思うその絶え間ない繰り返しが<知の銀河系>と言えるような膨大な量の書を生み出した。”
要するに、「知りたい」という利用者の願望、「知らせたい」という作り手の願望、それが膨大な知に広がる。僕はとても素敵な言葉だなと思っています。
■図書館は過去を保存する
(参加者から挙手)
さすがですね。ほとんど知っていますね。たとえば、私の住んでいる鹿嶋に、鹿島アントラーズというサッカーチームがいます。アントラーズがいる関係で、アントラーズの資料が図書館にたくさん置いてあります。そうすると、東久留米の方がこの中央図書館にお見えになって、「鹿島アントラーズの資料を鹿嶋の中央図書館から取り寄せてください」と言えば、特に難しい手続きがあるわけでもない。一定のルールの下で、その本は鹿嶋の図書館からこちらに届く、というシステムです。要は、冒頭言いました「備品」なんですよ。「備品」なんだけど、この世界は「どうぞ」ということで、全国、本が駆け巡っています。そしてまた、その本を利用者の方に届けるために、図書館員はとにかく一所懸命やっております。そんな世界というものをちょっと説明しながら話を進めていきます。
まず、利用者と図書館の関係であります。ちなみに、明日の僕のラジオには、和歌山県立図書館の司書の方が出演をいたします。なぜ和歌山の方が出るのかというと、僕は4月に那智勝浦という所からお仕事をいただいて、講演に行きました。その時に、わざわざ講演を聞きに来てくれました。そこで知り合いになって、いろいろとお話をしていく中で、ラジオに出てくれないか、というお話になりました。もともとこの方を那智勝浦に「講演があるから来ないか」と誘った人は、去年、東京の明治大学で行われた、図書館関係者が年に一回集まる「全国図書館大会」で僕がお話をする機会がありまして、それを聞きに来てくれた方です。そこからまたつながっていったという縁なんですね。とにかく、この世界は「人」とつながっています。先ほども申し上げたような、相互貸借のように制度的にもつながっています。それから、人もつながっています。今日も実は、宮崎県から来ているんですよ。私が直接つながっているんじゃなくて、僕とつながっている人とつながっているということで、「わざわざ」という言葉を使ったら失礼かもしれませんが、宮崎県から県の職員の方が今日はお見えになっています。こんな感じでつながっている世界なので、利用者の方々に色々なことが差し上げられる。「情報」がそうです。そういったものを是非味わっていただければ、絶対「これは悪い所ではない」とお分かりになるんじゃないかと思います。そして、「悪い所ではない」ということは「支えなくちゃ」というお気持ちにもなるんじゃないかという気がします。
『図書館のめざすもの』という本がありまして、これはどの図書館にもよく置いてあります。これは、図書館情報大学の名誉教授・竹内先生が訳し、また書かれたものなんですが、「アメリカ社会に役立つ図書館の12か条」というのがあるんです。もちろん「アメリカだから」という話じゃなくて、日本にも十分にこれは同じことが求められます。最後の12か条目に、僕の好きなフレーズ「図書館は、過去を保存します。」という言葉があります。そうなんです。図書館は、ひたすら過去を保存するんです。
この図書館(東久留米市立中央図書館)に来た時に、「あーよかった。いい図書館だな」と思ったのが、図書館に入って来たらすぐにお迎えしてくれたのが郷土資料だった。僕はこれが好きなんです。僕が3,4年前までいた塩尻の図書館もそうです。一番いい所、メインの所には、その町の最も売りにしている―塩尻だとワインや漆器だとか―が置いてある。そうすると、黙っていても分かるんです。この町は、ワインが有名なんだ。漆器が有名なんだ、と。黙って入ってきても、ここは「水」だと分かりますよね。「郷土資料が大切にされているな」と思いました。実は、図書館という役所の仕事、色々な行政のセクションがありますけれども、特にこの図書館というところは、郷土に関係する資料を徹底して集めて保存しています。ですから、「守られて」います。
僕が塩尻にいたときに、こんな例があったんです。僕は全く縁もゆかりもない塩尻という所に呼ばれて、図書館を作りに行った「外様」でした。ある方が訪ねてきて「今度の館長さんは茨城から来たんだって?あなたは郷土の資料についてどう思いますか?」と言われたので、私は「図書館というところは過去を保存する所なんですよ。お預かりした資料をもし頂戴できるのであれば、ずっと恒久的に僕はとっておきますよ。」ということを申し上げました。そうしたら、たびたび、ご自身が集めた地域関係の資料コレクションを、かなり持ってきていただきました。
なぜ僕のところに持ってきてくれたかというと、ある役所に、お尋ねになったらしいんですね。その郷土の関係の資料の最も近い町に持っていった。要するに、この資料に書かれている町がその町みたいだったので、そこに行かれた時に「それはちょっとできません」と。というのは、図書館がない町だったんですよ。ですから「責任もってお預かりできない」ということだったんですね。そして、少し離れた塩尻にやってきました。塩尻は図書館があります。ですから、「図書館は仕事としてそれを守ります」ということで、その資料をいただけることになった。
図書館という所は、本当に「地域資料」に関しては、徹底して大切にする場所です。ですから、どうぞご安心してください。図書館にさえ来ればなくならない。これが図書館と地域との関係ですね。
■図書館と出版界
ちょうど2000年のころに、そういった話がポツポツと出てきました。私がちょうど図書館を希望して異動になったのが40歳のときでした。役所に入って18年経ってから図書館に移ったんですけれども、もっと図書館と出版界って仲が良くていいはずだと僕は思っていたんですよ。なんで図書館はそんなに悪い悪いって言われるんだろう、と。そんな時に、たまたま僕が「読書アドバイザー」という資格を持っていた関係で、「図書館情報大学の大学院を受けないか」という話をある方からいただいた。「社会人入試があるからやってみないか」と。それだけで、受けたわけじゃないです。「図書館界と出版界と、なんでこんなにいがみ合わなきゃいけないのか。これを研究できないだろうか」ということが僕が進学した理由なんですね。出版界と図書館というものが、僕の研究テーマだったんです。
今年になっても、そういった出版界と図書館界の関係の特集やイベントが行われています。ちょうどレジュメの1ページのところだと、『選択』という雑誌。これは、会員制の雑誌で書店に並ばない雑誌です。なんとすごいタイトルなんですよ。《すさんでいく「公共図書館」》。荒んではいないだろうと思うんですが。それから『新潮45』の特集、《出版文化こそ国の根幹である》。これは確かに、国の根幹だと思います。さまざまな識者の方が、ご意見を述べていました。それから、イベント的なものとしては、日本出版クラブで《図書館は出版業界の救世主となり得るのか!?》。これは、僕は聞きに行きました。それから、結構話題になった《公共図書館は本当に本の敵?》。かなり刺激的なタイトルが並んでいますよね。
それで、つい最近、この『出版ニュース』という一般の書店や図書館で置いていない逐次刊行物に、元町田市立図書館長をされていた手嶋孝則さんという方が「図書館界と出版界との相互理解のために」というタイトルで論文を書かれています。いい論文で、今ちょっとお話をしたようなことを、手嶋さんなりにいろいろと、解説をしております。それで手嶋さんが最後にこんな風に結んでいるんですね。
“図書館の利用者が、個人で図書館を使っている人が多いために、ロビー活動があまり広がりを見せない”。
「ロビー活動」というのは、よく議員さんを通して「なんとか図書館を充実してください」と頼むやり方ですね。で、“これが、読書が、個人的な営為であることに由来していると思われるけれども、図書館利用者も、自分が利用する図書館を、よくする活動に加わることが求められる”という風なことを、最後に言っているんですね。確かに個人的な活動です。「個人で楽しめばいいじゃないか」と。でも、やっぱりそれだけだと、なかなか「明日の図書館」にはならないんですね。「明日の図書館」として、全国的に「このまちの図書館すごいよ」っていうのは、これはやはり、市民の方が「支える」というエネルギーになっているっていうことが、僕は大切なんじゃないかと思っています。
■図書館権利宣言
2年前の2013年、アメリカ図書館協会がこの権利宣言を書いた。これが、図書館が主語になって「私たちがこんなことをしてあげます」ではなく、「私たち市民の生活がどう変わります」とか「私たちがどういう権利を持っています」という、主体が「市民」になっているのが結構あるんです。図書館は「本を単純にタダで借りるところ」だけじゃないんですね。多くの方が「図書館って、なあに?」って聞くと、「本をタダで借りられる場所」と仰るんですが、とてもとてもそれだけだと言い尽くせません。むしろ、もっとご自身の精神や地域を豊かにしていく所です。そういうことが、ここに権利の宣言として書いてあります。
たとえば、5番は“地域をつくる図書館 図書館は面と向かって、あるいはオンラインで、その地域の住民同士のコミュニケーションを促進することで、利用者がお互いから学び合い、お互いを助け合う場を提供しています。図書館は、お年寄り、移民―これはアメリカだからですね―、その他特別のニーズを抱える人々を支援します。”と書かれています。お互いから学び合うっていう場所でもあるし、お互いを助け合う場としても提供しているんですよ、ということがここに書いてある。
それから、6番「知る権利を守る図書館」ということが書かれています。”我々に与えられている、読む権利、情報を得る権利、そして言論の自由は、始めからあるものではないということを認識しなければなりません。図書館と図書館司書は、アメリカ合衆国憲法修正第1条で保障されているこういった最も基本的な権利や自由を積極的に守る役割を担っています”。ここで、「図書館と図書館司書が」っていうところ、最後にもう一回出てきますので、よく覚えておいてください。
そして、ここの10番が、先ほどちょっと紹介しました『図書館のめざすもの』の、「アメリカ社会に役立つ図書館の12か条」の12番目と似ているのは、「文化資産の保全に貢献する図書館」ということで、“過去は未来の礎です。図書館は過去、現在、そして未来をより深く理解するために必要な歴史的な文書の原本の収集、デジタル化、そして保存します”と書いてあります。
ですから、お時間があるときにはちょっと他のところも読んでみていただきたいんですけれども、図書館というところは、ものすごいエネルギーを持っているところです。そして、ものすごく豊かなポテンシャルを持っています。ただ、市民の方々は、それをもしかしたら使いこなせていない。もちろん、知らないという方もいるかもしれない。図書館は色々な方法を使って図書館サービスを周知しようとしていますが、ただ、やはりなかなか通じないところもあります。
■貸出数と選書
たとえば、大道珠貴さんの芥川賞の受賞作『しょっぱいドライブ』。もしかしたらお読みになった方もいらっしゃるかもしれません。2002年の受賞作です。これがですね、ちょっと見にくいと思うんですが、(本を掲げる)松浦寿輝さん。東大の学者ですけれども、『知の庭園』という本を書かれて、これは「芸術選奨」を獲った。1999年の芸術選奨の受賞作です。どちらかというとこれは「専門書」という言い方をされます。
2003年に「図書館がどうもおかしいな。選書がヘンだな」ということになって、図書館協会と日本書籍出版協会が合同で調査をしました。全国の図書館の約25%くらいが回答をしましたので、大体そう大きくは現実と違わない。ただスケールとしては25%ですから、1/4のスケールモデルということで聞いてもらいたいんですが、その調査時で、この芸術選奨受賞作、松浦寿輝さんの『知の庭園』というのは、6.5%の44館でしカ所蔵されていない。ところがですよ、こちらの大道珠貴さんの所蔵館は821館あった。そうすると、『しょっぱいドライブ』と、『知の庭園』の差は約19倍です。
「だって、『しょっぱいドライブ』はたくさんの人が借りるし、『知の庭園』は誰も借りないよ、難しいんだから。」と思ってる司書がいたら大間違いです。調べましたところ、『しょっぱいドライブ』の1冊あたりの貸出数が5.7回でした。『知の庭園』が5.5回でした。変わらないんです。もちろん、これはあくまで一例ですけれども、「芥川賞作品は借りられる、芸術選奨は借りられない」というのは、これは違います。何が言いたいかというとですね、『知の庭園』は、なんと、その統計の時に2,600部しか刷られていないんです。『しょっぱいドライブ』は今文庫本でも出ています。『知の庭園』に出会えるチャンスが、どれだけないか。少なくとも、私の家のある茨城の鹿嶋にはこの本は置いていないです。
図書館も書店も、基本的には読者の方に本を届けたいんです。もちろん、書店は書店なりの理由があります。当然、限られた店舗でそんなに全部は置けるわけではありません。そうなってくると、当然「なんとか図書館が頑張ってくれないかな」もしくは出版社でも「図書館に入ってくれないかな」と思っている。
でも、もしかしたら図書館では、そうじゃないかもしれない。僕は塩尻で本の選書をしているときに「これ、借りる人いるかねえ」なんていう言葉が聞こえてきたら、言っていました。
「関係ない。図書館が、塩尻が取っておくと思った本は買っていいんだ。図書館は、過去を保存するところなんだよ。」
もちろん、すべての過去は保存できません。あくまで、身近な郷土資料からですけれども。「いいと思ったら、図書館は買わなきゃだめなんだ。だって、少ない部数の本を届けられるのは、小さな書店では無理、田舎じゃ無理なんだ」と、僕が行ってからは、そういう風に塩尻の職員には言いました。図書館というのは出版文化というのを守るところ、というお話です。
さて、「図書館は誰のものか」といえば、もう当然、皆さんのものです。皆さんが自分のものだと思っていいんです。そして、「自分のライブラリーを作ってみたいな。小さなライブラリーでもいいから作ってみたいな。」と思ったのが、今日のイベントです。
■カーネギー・フォーミュラ
カーネギーは、「善意の裁量の分野は、一番もっとも大事なのは大学である」と言っています。「二番目が図書館。そして三番目が、医療センターである」。そして、その莫大な財産を図書館建設に寄付するという形で、カーネギーは協力しました。アメリカで1,679館が、カーネギーの援助を受けています。日本の公共図書館は3,250。半分です。それぐらい、カーネギーは私財をなげうった。
ただし、僕がすごいと思うのは、ちゃんと「条件」ということを言っているのです。カーネギーは「カーネギー・フォーミュラ」という言葉を使っているんですが、何かというと、「図書館建設の費用の10%を、運営費として必ず用意をしなさい」「まちが公共図書館の必要性をちゃんと地元の方に説明をしなさい」そして「住民は無料である。これも約束しなさい」。要は、単純に「あげる」からではない、市民の方が「自分の図書館を守っていきます」と約束するんなら、私はどんどん寄付をしますよ、ということを言っている。「市民のものになる」「責任持って運営していく」ということを確認しています。一時だけ寄付金をもらって終わるわけじゃなく、ちゃんと永続的にやっていってくださいよ、ということを言っています。
そういったカーネギーの精神は、別にアメリカの話じゃありません。日本にだって十分に言えることです。ずっと図書館の世界の中では「図書館というものが市民のためのものだ」とは言ってきているんですけども、なかなか「近づいてきている未来」にならない、というところは、全国歩いていまして、感じています。でも、このイベントのお声をかけてもらったとき、単なる講演だけじゃなくて「ひとハコフェス」と聞いたときに、「これはすごいな」と思いました。また、これだけの参加者・出展者がいたということ、たくさんの方が図書館に関心を持っているっていうことも、素晴らしいなと思っています。
■図書館は教育機関
最後に配布資料をちょっとご説明させていただきたいと思います。これは『New York』というタウン紙に『The New York Times』の写真が載った新聞広告です。写真は1954年の5月18日付の『The New York Times』です。そして問題はその前日の日付のこの記事。“HIGH COURT BANS SCHOOL SEGREGATION”。何かというと、最高裁が下した「ブラウン判決」です。長らくアメリカを苦しめていた、黒人と白人が公立学校で別々に教育を受けていることに対して、「一緒に学ぶべきだ。学ばなきゃおかしい」という判決を出したんですね。この広告を出したのは、New York Pulic Libraryです。
“One of the Library’s greatest stories.”
「図書館のたくさんある偉大なる物語の中のこれはたった一つなんだ」。
図書館がどれだけのことをやったか。図書館で学んだ人たちが、「これはおかしい」と気付いてくれて、そして、世論を動かした。これは図書館の「勝利宣言」ということを、堂々と広告を出した。しかも1954年にですよ。これが、いかにアメリカで図書館が根付いているか。図書館が過去を大切にし、過去から市民が学び、おかしいと思ったことはおかしいと訴えていく、そして何らかの世論に流れていく、そういった力がある所なんだと、この広告で言っているんですね。それで、最後の”so many ways”で始まるところは、「多くの方法によって、The New York Public Libraryはアメリカを教育するための手助けをしています」要するに、図書館はれっきとした教育機関です。
最近ちょっと「教育機関にしてはおかしい」と思うような図書館が出てきているので心配なところはあるんですが、図書館はれっきとした教育機関です、ということもお伝えして、最後にちょっと写真をご紹介していきたいと思います。
■写真とさまざまな取り組みの紹介
(お持ちになった写真についてお話いただいた内容)
●塩尻市市民交流センター外観
私が5年間勤務をしオープンに立ち会いました長野県塩尻市立図書館が入っている「市民交流センター」という複合施設です。全体で1万2千平米、図書館が3千3百平米ですから、地方の都市にしてはかなり大きいです。
●塩尻市立図書館のカウンター(水のペットボトル)
塩尻が普段からやっていることの一つなんですけれども、これは図書館のカウンターです。塩尻には水道事業というのがありまして、ここは企業会計ですからお水を作って売っています。水道課に水が置いてあっても、そんなに水道課が好きで毎日行く人はいませんよね。こういったものも図書館という場を利用すれば、やっぱり、「図書館が好きだ」っていう人がいれば、図書館に来ることでまちのプロダクトが分かるし、また、来客、市外から来た方も、「あ、こういうもの作っているんだ」ということが分かる。
●塩尻市立図書館・ワインのコーナーの書架
一番人通りの多いところ、「塩尻のメインストリート」の書架です。ワインや漆器のグラス、色々な役所の販売物が置いてあります。それから外国語の資料も置いてあります。
●新着図書の背表紙コピーをはった壁面
一か月にどんな本を買ったのかが分かるように背表紙を全部カラーコピーでとっています。複合施設ですから図書館の「外」にこれを貼ることで、図書館に来ない人も「図書館はこんなに買ってるの?」と分かるように貼っております。これは壁柱といって書架に見えますが書架じゃありません。
●展示スペース/今村幸治郎氏のイラスト
今村幸治郎というイラストレーターがいます。宇都宮に在住でフランスの「シトロエン」という車しか描かない人なんです。このシトロエンのイラストレーターが僕の知り合いなものですから、塩尻でこの方の作品展をやりたいということで、相談に行きました。
●ミニカーの展示風景
なんとか議会にも予算を認めていただいて、展示会ができるようになりました。その時に市民の方が私を訪ねてきて「ミニカーを一万台ほど持っているんで、シトロエンの展示で協力しようか?」と。展示ケース3つに、シトロエンのミニカーが並んだんですね。そうすると、図書館に来たことない方が「ミニカーが見たい」と来るようになります。すると、意外なほど自分が思っていた図書館のイメージと違う。本がある。CDもある。「ある」というのが分かる。
●内野氏愛車シトロエン
そして、これが僕のシトロエンです。
●スバル360
スバル360という車があって、ご年配の方は分かると思いますが、日本が経済成長を遂げているときに、「マイカーがもしかしたら自分にも持てるかもしれない」という庶民の夢を叶えてくれた車です。今の値段に換算したら500万です。
●『スバル360を創った男』の書影
『スバル360を創った男』という本があります。百瀬晋六さんという方が塩尻の出身だということを僕は知らなかったんです。市民の方がこれも教えてくれました。でも、<外様>じゃない他の図書館員も知らなかったんです。東京大学に進んで航空工学を学んだんですが、戦争が終わってしまったんで、富士重工に入って、車を作った。NHKの『プロジェクトX』にもなっています。ただし、その時には「塩尻出身」というのは出なかった。
●スバル360のミニカー
これもやっぱり「スバル360だけ並べよう」ということで、やってくれました。
●ジャンボ機プラモデル
そうすると、それを見た人が、他の市民の方が当然黙っていません。「ミニカーごときには負けない」という方が出てきます。当時松本空港を就航していた小さな飛行機・YSを見て、松本近辺の子供たちは、「飛行機ってでかいなあ」と言ってた。羽田や成田はもっとでかい飛行機が飛んでいる。同じスケールモデルで並べて、これだけ実物が違うってことを子供たちに見せたかったというんです。これも、ずらっと並んで壮観でした。そして、もちろん図書館ですから、飛行機が並ぶときには飛行機に関する色々な本を並べます。そうすると、普段動かなかった本がたくさん動きます。
●飛行機の展示の様子
●サンダーバードの展示
そうすると色々な方がやって来て、「サンダーバードなら負けない」という方が出てきました。そうすると、図書館が「市民の方のもの」になるんですよ。それまで、この展示ケースには、図書館の貴重な本を展示していました。
●塩尻市立図書館の書架
とにかく利用者の方に資料との出会いの確率を高めたいと言うことで、塩尻の配架方法の一つとして本とDVDとCDは同じ場所に置くようにしました。
●オガール紫波町の市場
岩手県の紫波町というところで、隣りが市民マーケットみたいなところです。そこに「この材料を使うとこんな料理ができる本が置いてあります」ということを、至る所に貼っています。そうすると見た人が、「図書館に行って本借りよう」となります。
●貸出ぬいぐるみの写真アルバム
岩手県一関であったものです。ぬいぐるみを貸す図書館っていうのは少なくないのですが、ぬいぐるみにはバーコードが貼れません。ここでは写真を撮ってぬいぐるみの一点一点の特徴を書きながらアルバムをつくるという管理の仕方をして、貸出をしています。
●熊本県菊陽町の「その他の外国語」書架
九州熊本の菊陽町というところです。すごく明るい書架に見えませんか?ここの書架は、外国語に関連するようなイメージで書架に万国旗の絵を貼り付けて、遠くから見ても、そこにどんな本が置いてあるのか分かるようにしています。
●「あの人へ送る手紙」展示
「手紙」じゃない、「あの人へ送る手紙」というサインにして、ペンのイラストをあしらっています。
●北海道・恵庭市/ぬいぐるみの座るベビーカー
普通はぬいぐるみがない状態でベビーカーが置いてある図書館はあります。でも、無味乾燥です。このようにベビーカーにぬいぐるみを置いただけで、オブジェになります。かわいい雰囲気になります。何気ないんですけど、こういう配慮もいいと思いました。
●アメリカ・ジグソーパズルの棚
アメリカの図書館にあった「ジグソーパズルを貸し出している図書館」ということで、これは私も国内では見たことがないですね。
●カード
アメリカの図書館の決して大きくない図書館の壁に貼ってあった、さまざまな講座の案内です。”Business & Investing”「仕事と投資」とあります。色々な講座の内容です。例えば、”Retirement Plannning”「退職の計画」、”Goal Setting”、「終活」、”Financial Planning”、どうやってお金を蓄財するか、それから”Investiment 101”、投資をどうやってすればいいのか、”Creating Positive Future”、活き活きとした人生をどうすればいいのか等、さまざまな講座がいかにも生活そのものになっている。だから、図書館に行けば何かが得られる。図書館に行けば、誰かに会える。図書館に行けば、同じ悩みを共有している人に会えるかもしれない、というまさに生活に根付いているというところです。
●ボックス
”HELP YOUR COMMUNITY” 「この地区の皆さん方の、コミュニティの中の人を助けてください」”Please donate”ですから、「どうか寄付をしてくれませんか?」「ツナでもいいです。ピーナツバターでもいいです。クラッカーでもいいです。いただけませんか?」ということを図書館でやっている。ああ、まさに、「図書館はこういうところなんだ」と、しみじみと感じ入ったところでございます。
拙いお話で大変申し訳なかったんですけれども、お付き合いいただきまして、ありがとうございました。
■質疑応答
図書館は公が担っていくのがこれまでは主流だったんですけれども、これは全国的な流れかどうか分からないんですが、指定管理者制度が導入されて、民間の会社が管理するという流れになっていると見ています。いいか悪いかという議論は様々あろうかと思うんですけれども、内野先生が今まで見てきた中で、公が担っている図書館と民間が管理している図書館とで、大きな決定的な一番の違いっていうのは、何か一言で教えていただければと思います。
内野氏)
この場で直営がいいのか指定管理者がいいのかという議論やお話をするというのは適当でないと思います。ただ、一つ事実だけ申し上げますと、いま指定管理の図書館というのは公共図書館の12%ぐらいになっているかと思います。
実は私も、指定管理者だけの前で講演をやることもあります。そして、こんなことを言われたのが凄く印象に残っているんです。これは、直営の方にはちょっと申し訳ないのですが、敢えて聞いていただきたいんです。塩尻ではこんな風に言っていました。「お客さんが見えたら“ありがとうございます”“こんにちは”を必ず言おう」。ちゃんと言おうね、と。そんな話を民間の館長さんがいる前で言ったら、終わった後の懇親会で「内野さん、一つだけ納得できない。<ありがとう>って普通では?私たちは普通に言うんだけど」と、言われたんですよ。
確かに役所だと、言わない人が残念ながらいます。新聞社のコラムニストの方が、私の拙い本を読んで「図書館は<人>なんだ」と気が付いた。施設でもない、資料費でもない、要は<人>だというところに行きつくとすれば、それは直営だろうと直営じゃなかろうと、いずれにしても、図書館は<人の情熱>で運営されるところだと僕は思っています。
その<人>を育てるのは、僕は市民の方だと思います。市民の方しかいません。そういう関係ができれば、僕は運営形態は関係ないのではないかと思います。ちょっと怪しいところもあるにはありますけれど、そこは勘弁してください。
●質問2
私はすごく図書館は好きなんですけど、いっぱい活字を読むのが苦手なので、気軽に来れるといいなといつも思っています。最近、スターバックスとか入った図書館が、ありますよね。すごく面白いなと思うんですけど、見学されたことはありますか。ユーザーとか職員さんの、いいと思ってるところと悪いと思ってるところ、ああいう民間、カフェが入ったところってどうなのかなというのがとても気になっているので、ちょっとそういう意見を聞いたことがあれば、ぜひ、教えていただきたいと思います。
内野氏)
武雄の図書館は見に行っております。それから、今日の資料に載せている『選択』という雑誌で書かれている小論に武雄のことが書かれています。今のご意見などは皆さんもご存知だと思いますけれど、私も見に行って、考えるところはありました。ただ、ここでそれをどうのこうのは言えないのですが。
図書館が変化していることは確かです。かつては図書館の中は絶対といっていいほど飲食は禁止でした。なぜかというと、間違ってもし倒れてしまったら当然資料を汚してしまう。しかし今は、ペットボトル(蓋付き)であればいいというところが増えています。もともと水を飲む行為を禁止しているのでも、喉が乾いたら外に行けと言ってるわけでもない。もしかしたら貴重な備品・財産が守れなくなる可能性があるので、ルールを作ったんです。利用する側の方がちゃんとルールを守るということが浸透していることは確かだと思います。ですから、比較的許可をしてきている。
日本の図書館は”Don’t”「するな」と”No.”が多い。でも僕がアメリカで行って見てきた図書館は、ほとんどのポスターが”Please”なんですよね。「~してください」「協力してください」。「するな」じゃないんですよ。ある象徴的なことがあったんです。子供さんが、図書館を走ってたんです。日本の図書館は、職員が追っかけてますね。「こらこらこらダメダメダメ。走っちゃダメ」と言いますけど、その時、アメリカの図書館員は何をやったと思います?その男の子の脇を”Walk,walk,walk.”とゆっくり歩く。そうすると、その男の子が、”Walk,walk”と真似する。そこで”OK.”。ルールさえ守れれば、色々なものがどんどん解禁されていく。そうなってくると、カフェが図書館にあったって、何らおかしくはないと思います。
図書館自体は、色々な方に来てもらいたいと思っています。ただ飲食というのが、制度的に非常に難しかった。昔は自動販売機すら置くことができなかったんですよ。「誰が電気代をもつのか」もしくは「こぼされたら誰が掃除するのか」、そんなマイナスの要因がすぐに働いちゃうので、結局は「ダメ」。最初は「いきなりはダメ」になるんですけど、でも、結局皆さんが協力し合って、この施設、このサービスを、維持向上していこうっていう関係性ができてくれば、色々なことが解禁されていくんじゃないか。僕はもっともっと解禁されていくはずだと思っています。それができるような図書館になれば、そこは、利用者が利用者の方を注意するかどうか。ちゃんと「ダメよ」と言ってくれるかどうか。もしくは、それをみんなが聞くっていう形になっているか。そうなったら、素敵な図書館になるだろうとは思います。
※このページの講演内容は東久留米市立図書館が記録を作成し、講師に許諾を得て掲載しています。
無断転載・無断コピーはおやめください。
■紹介された文献等
『2005年の図書館像 地域電子図書館の実現に向けて(報告)』文部省地域電子図書館構想検討協力者会議 文部省 2000.12
『新集知の銀河系 図書館情報大学講演録1~4』筑波大学大学院図書館情報メディア研究科/編 日本図書館協会 2004.8
『図書館のめざすもの 新版』竹内 哲/編・訳 日本図書館協会 2014.10
“すさんでいく「公共図書館」 武雄市「TSUTAYA」委託が最悪例” 『選択』2015年2月号 選択出版株式会社 2015
“「出版文化」こそ国の根幹である” 『新潮45』2015年2月号 新潮社 2015.1
“図書館は出版業界の救世主となり得るのか!?” 日本出版クラブ 2015年1月30日
“公共図書館はほんとうに本の敵?” 日本文藝家協会 2015年2月2日
手嶋孝則 「図書館界と出版界との相互理解のために」 『出版ニュース』2015年5月中下旬号 出版ニュース 2015.5
このページに関するお問い合わせ
教育部 図書館
〒203-0054 東京都東久留米市中央町2-6-23
電話:042-475-4646 ファクス:042-475-6631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
