東久留米を調べる
ページ番号 1025076 更新日 令和8年1月20日
基本資料
(図書)
1.『東久留米市史(本編)』 東久留米市 1979年
原始時代から現代にいたるまでの市の変遷を明らかにしたものです。
2.「東久留米のあゆみ」シリーズ 東久留米市教育委員会
1979(昭和54)年に発刊された『東久留米市史』を原点に写真や資料を多用し編集しています。
(第1巻)『東久留米のあけぼの:考古学にみる東久留米市の原始時代』1999年
(第2巻)『東久留米の江戸時代:文化財からみた東久留米の村々』2005年
(第3巻)『東久留米の近代史:明治・大正・昭和前期の歴史』2012年
3.「東久留米市歴史ライブラリー」シリーズ 東久留米市教育委員会
『東久留米市史』や『東久留米のあゆみ』シリーズの内容をさらに深く掘り下げ、個々の歴史や文化財に焦点をあてたシリーズです。
(1)『東久留米の戦争遺跡:戦争の惨禍を語り継ぐために』2019年
(2)『東久留米の古地図:明治時代地引絵図を中心として』2020年
(3)『東久留米の学校史:明治・大正・昭和・平成』2021年
(4)『東久留米の近代歴史文書:近代行政文書を中心として・明治時代編』2023年
4.『東久留米市文化財資料集』 東久留米市教育委員会 1973~1991年
市内の先人たちの文化の足跡を分野ごとにまとめています。
(1)寺社編 1973年
(2)古文書目録編 1974年
(3)板碑編 1975年
(4)講編 1976年
(5)民家編 1977年
(6)寺社建築・美術編 1978年
(7)石仏編 1979年
(8)東久留米の遺跡 1980年
(9)地名編 1983年
(10)板碑編改訂版 1985年
(11)絵馬編 1988年
(12)指定文化財 1990年
(13)東久留米の年中行事 1991年
5.『統計東久留米』東久留米市(年1回刊行)
市の人口、産業、経済、文化、厚生等の各分野にわたる基本的な統計資料を集約し、市の現況を表しています。市制となる1970(昭和45)年以前については『町から市へ~現況と推移』をご覧ください。2010(平成22)年版以降は市HPでもご覧いただけます。
6.『かんきょう東久留米』東久留米市(年1回刊行)
市の環境の現況データと、豊かな自然を次世代につなげていく様々な取組の状況を示しています。2001(平成13)年度以前については『東久留米の公害』(東久留米市)をご覧ください。2015(平成27)年度以降は市HPでもご覧いただけます。
7.『社会教育のあらまし』東久留米市教育委員会(年1回刊行)
市の教育委員会における事業の取り組み実績を年度ごとにまとめたものです。東久留米市立図書館の取り組みを辿ることもできます。過去3年分を市HPでもご覧いただけます。
8.『光の交響詩』東久留米市教育委員会 2000年
明治から東久留米が大きく変化する昭和40年代中頃までの移り変わりをつづった写真集です。
9.『地誌 ふるさと東久留米』 東久留米市郷土研究会 1995年
代々受け継いできた東久留米の人々の風俗や歴史を、市内郷土研究会の方々がまとめたものです。
10.『くるめの文化財』東久留米市教育委員会(不定期刊行)
旧石器時代より人々が住んでいた東久留米には様々な歴史や文化があり、それらを物語る文化財が残されてきました。その中で市文化財として指定されたものについて、紹介・説明しています。
(地図)
1.『東久留米市都市計画図(1:10000)』東久留米市 1968年~(所蔵がない年あり)
土地利用や都市整備および市街地開発に関する計画を図面化した地図です。そのほか、市が作成した地図は『東久留米市都市計画道路網図』『東久留米市道路線認定網図』『東久留米市水路・河川網図』があります。
2.『明治時代各村地引絵図 1・2・3』 東久留米市史編纂室/編 東久留米市 1975~1976年
明治政府が行った地租改正のための土地測量図である地引絵図の復刻版です。
3.『ゼンリン住宅地図東京都東久留米市』ゼンリン
1985(昭和60)年発行分から現在に至るまでを所蔵しています。
そのほか、昭文社が発行する「都市地図」や国土地理院の「地形図」などでも東久留米の移り変わりを知ることができます。地図資料についての詳細はパスファインダー(調べ方案内)もご覧ください。
(広報紙)
『広報ひがしくるめ』東久留米市
東久留米市が久留米町であった1968(昭和43)年10月発行から現在に至るまでの広報の原紙を所蔵しています。また、久留米村であった1956(昭和31)年6月発行から1997(平成9)年4月15日発行までの広報は縮刷版でもご覧いただけます。2003(平成15)年8月1日号(第872号)以降の広報は市HPでもご覧いただけます。
東久留米市に関する新聞記事索引
図書館では、1984(昭和59)年より、朝日新聞、東京新聞、毎日新聞、読売新聞の東久留米市に関する新聞記事を切り抜き、分類をつけ、原紙を保存しています。
さらに、年単位で記事の見出しを索引とし、分類別、日付順の『東久留米市に関する新聞記事索引』を発行しています。
パスファインダー(調べ方案内)
パスファインダーとは、あるテーマについて調べるときに役立つ基本的な資料や情報源、情報の探し方・調べ方の案内です。
よくあるお問い合わせを中心に、所蔵資料の中から調べものに役立つ資料を紹介します。
-
「東久留米の戦争の記憶」を調べる (PDF 918.6 KB)

-
「東久留米駅」を調べる (PDF 226.8 KB)

-
「東久留米の自然」を調べる (PDF 950.7 KB)

-
「東久留米の学校」を調べる (PDF 874.7 KB)

-
「東久留米の遺跡」を調べる (PDF 876.6 KB)

-
「東久留米の地図」を調べる (PDF 896.1 KB)

-
「東久留米の川」を調べる (PDF 906.5 KB)

-
「東久留米の農業」を調べる (PDF 151.1 KB)

-
「東久留米の団地」を調べる (PDF 248.2 KB)

-
「群馬県榛名地域」について調べる (PDF 351.4 KB)

しりたいひがしくるめブックリスト(子ども向け)
新着de Reference(地域資料)
新しく受け入れした地域資料を紹介する「新着de Reference(地域資料)」を発行しています。
(参考図書と交互に発行しています。)
2026年
2025年
-
No.223(2025年11月発行) (PDF 132.1 KB)

-
No.221(2025年9月発行) (PDF 131.0 KB)

-
No.219(2025年7月発行) (PDF 129.0 KB)

-
No.217(2025年5月発行) (PDF 122.6 KB)

-
No.215(2025年3月発行) (PDF 520.3 KB)

-
No.213(2025年1月発行) (PDF 115.8 KB)

ブックリスト
東久留米にまつわるおはなし
久留米の里
江戸の昔、武蔵の国では黒目川のことを久留目川と呼んでいました。来目川や来梅川と書くこともあります。
それが明治になると、いつしか久留米川になったのです。目の字が米に変わるのです。湧水の多いこの地は、豊かな水とともに人々の生活が成り立っていたのですが、稲作だけは不向きな土地でした。湧水が直接出てくるので、川幅が狭く、水温がやや低いためです。お米のできない村もありましたし、できても農業生産の2割ほどがやっとでした。そんな水稲耕作のやりにくい土地なのに、どうして久留目の目が米に変わったのでしょうか。それは、想像ですが、明治という時代背景にあったように思われます。昔から、お米は、ある意味で富の象徴でした。新しい時代の新しい息吹、そんな明治の雰囲気を肌で感じた当時の人々は、農村の豊かさへの希望と祈りを「米」という字にこめたのではないでしょうか。そして、明治22年、10の村が集まって、この久留米川の名前をつけた「久留米村」が誕生したのです。
時は移り昭和初期、稲の生産高は4倍になり、小麦は東京府下で1位の生産実績をあげるようになったのです。
久留米の名に込められた、当時の人々のその情熱と努力を、いつまでも忘れないで学んでいきたいと思います。
文責:山崎 丈
(東久留米市郷土資料室学芸員)

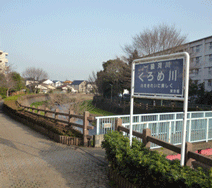
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。
このページに関するお問い合わせ
教育部 図書館
〒203-0054 東京都東久留米市中央町2-6-23
電話:042-475-4646 ファクス:042-475-6631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
