図書館フェス2021 本屋さんのトビラ
ページ番号 1025138 更新日 令和6年12月27日
本屋さんのトビラ
図書館フェス2021にご参加いただいた本屋さんの紹介ページです。
魅力あふれる本屋さん、古本屋さんのコメントをご覧ください。
※ホームページのURLの公開は終了しました。
◆ 質問 ◆
☆お店のご紹介
Q1.おすすめの1冊を教えてください
Q2.今の仕事をするきっかけとなった事柄や本を教えてください
★お店(出版社)を利用される方へのメッセージ
magnif(マグニフ)

お店のご紹介
古本の街、神田神保町に店をかまえる古書店です。ファッション雑誌を中心に、国内外の様々な雑誌を集めています。
Q1.おすすめの1冊を教えてください
『'80sガールズファッションブック』竹村真奈 グラフィック社
80年代のファッションや雑誌の誌面などがいっぱい詰まったビジュアル・アーカイブ集。
この一冊でファンシーな'80sの魅力の知ってもらって、当時の雑誌等にさかのぼる手がかりにして欲しい。
Q2.今の仕事をするきっかけとなった事柄や本を教えてください
通った大学が神保町周辺にあり、それからこの街から離れられなくなりました。旧い本、旧い建物、旧い町並み、どれも魅力的です。
お店(出版社)を利用される方へのメッセージ
神保町は数多くの古書店が集まる“古本の街”です。それぞれの店がそれぞれの専門性を持っているので、何かしらの出会いがあるはずです。ぜひお来し下さい。
よもぎBOOKS
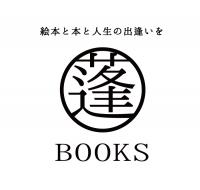
お店のご紹介
2017年3月3日、東京都三鷹市にオープンした小さな本屋です。山梨県にあるギャラリーカフェ・ナノリウムに本棚を間借りして販売したり、WEBショップでも販売しています。
絵本を中心とした棚作りをしていますが、作り手の体温が伝わるような本や、消費されるだけではなく何度も読み返したくなるような、思考に新しい示唆を与えてくれるような本をご用意しております。
Q1.おすすめの1冊を教えてください
『ルリユールおじさん』(いせひでこ/講談社)
ルリユールとは手作業で製本・装幀を専門とするフランス文化特有の職人のこと。
フランスではルイ14世の敷いた政令により長く「印刷」「製本」「出版」をひとつの会社でやってはいけないことになっていました。そのために「製本・装幀」に特化した職業なのです。
今ではIT化によりルリユールの数がフランスでも少なくなってしまったそうなのですが、自分の頭と手が直結するルリユールの仕事に憧れます。 余白があることでどこまでも絵が続いていく構図になっていて、どの角度から読んでも憧れる絵本です。ずっと棚に差しておきたい一冊。
Q2.今の仕事をするきっかけとなった事柄や本を教えてください
もともとは大型書店で働いていました。2011年の東日本大震災に妊娠・出産を経験し、それをきっかけに働き方を問い直すようになり、紆余曲折あった末に今の本屋を始めるに至りました。
『なんていいんだぼくのせかい』(荒井良二/集英社)の、どんな世界に置かれても声に出してすべてを肯定するという姿勢にいつも励まされています。
お店(出版社)を利用される方へのメッセージ
不思議なもので、本棚を眺めていると今の自分が何に興味を持ち、何を求めているのかがわかることがあります。その時々で必要とする本があるのだと思います。すこし疲れてしまった時、立ち止まりたい時。支えがほしい時。そんな時は、店内でご自身と本の対話のひとときを楽しんでいただけたら嬉しいです。
三輪舎&本屋・生活綴方
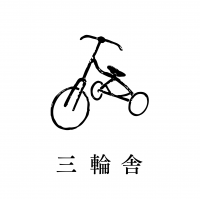
お店のご紹介
東急東横線妙蓮寺駅徒歩二分、横浜市港北区にある出版社「三輪舎」と、妙蓮寺のまちの本屋「石堂書店」と三輪舎が、2020年2月に開業した「本屋・生活綴方」です。商店の店主やお客さんの話す声、保育園のこどもたちや先生の賑やかな声が身近に聞こえる〈生活のまち〉で、わたしたちは本をつくり、本を届けています。その循環に興味を惹かれた、たくさんの有志スタッフ(「お店番」と呼んでいます)が集まり、みんなでお店を運営しています。本を売るだけでなく、「本を書く/つくる」(ZINEづくり)、「表現する」(展示)もできるように、印刷機やギャラリーも併設しています。
Q1.おすすめの1冊を教えてください
『火を焚きなさい』
野に生きた詩人に、火を焚きなさい、と何度もリフレインされるうちに、そうか、人間は火を焚くことができる動物だったのだ、と思い出す。
そしていつしか、薪をくべる先は私自身のなかにあることを教えられる。「山に夕闇がせまる/子供たちよ/もう夜が背中まできている/この日はもう十分に遊んだ/遊びをやめて お前達の火にとりかかりなさい」――私たちに薪のストックはあるだろうか。
Q2.今の仕事をするきっかけとなった事柄や本を教えてください
『山びこ学校』(岩波文庫)
昭和23年、山形の寒村に赴任した新任教師が編纂した「山びこ学校」という作文集があります。この本で提唱されている「生活綴方」という実践的な思想が当店の店名の由来になっています。「生活綴方」とは、ひとが自分自身の生活の中で見て、聞いて、観察して感じたことを自身の言葉で文章に表現することをとおして、新しいものの見方を獲得することを言います。この考えを軸にして本屋をつくってみようと思いました。
お店(出版社)を利用される方へのメッセージ
妙蓮寺は家族親戚あるいは仲の良い友人でも住んでいなければ訪れることのないまちです。でも、このまちに降り立ったひとはみな口を揃えて、このまちに住みたいと言います。ぜひ遊びにいらしてください。
青と夜ノ空

お店のご紹介
主に衣食住にまつわる本(新刊本、古本)をウェブショップにて販売。その他、移動本屋の開催やイベント出店、選書した本を送る企画「セレクト便」なども実施。
Q1.おすすめの1冊を教えてください
『いのちをむすぶ』(佐藤初女、集英社)
“食はいのち、食は生きることの基本です。”と仰っていた佐藤初女さん。
初女さんが人生の中で大切にしてきたこと、人が生きていく上で指針となるような考え方を伝えてくれています。読む度にその言葉に励まされ、新しい発見や気づきがある一冊です。
Q2.今の仕事をするきっかけとなった事柄や本を教えてください
青と夜ノ空をスタートするにあたり、『世界はうつくしいと』(長田弘、みすず書房)に収録されている「冬の夜の藍の空」という詩に出会いました。これは冬のキリッとした壮大な夜空の世界が描かれている詩です。
長田さんが私自身を応援してくれているような詩だと勝手に思い込み、勇気づけられたのをよく覚えています。
お店(出版社)を利用される方へのメッセージ
本はときに知らない世界を疑似体験できたり、ときに生活を豊かにしてくれたりします。
当店がそんな大切な本との出会いの場となることを願っています。
Title(タイトル)

お店のご紹介
荻窪駅と西荻窪駅のあいだにある新刊書店です。店の奥はカフェになっており、コーヒーを飲み、スイーツなど食べて、おくつろぎいただけます。2階はギャラリーになっていて、常に展示を行っております。不便な場所にありますが、わざわざ足を運んでいただく方も多く、ありがたい限りです。本好きの方が好みそうな本から、部数が限られている個人が発行したリトルプレス、子どもの好きなコロコロコミックや絵本など、本は硬軟取り揃えておりますので、ぜひ一度お運びくださいませ。
Q1.おすすめの1冊を教えてください
荻窪駅と西荻窪駅のあいだにある新刊書店です。店の奥はカフェになっており、コーヒーを飲み、スイーツなど食べて、おくつろぎいただけます。2階はギャラリーになっていて、常に展示を行っております。不便な場所にありますが、わざわざ足を運んでいただく方も多く、ありがたい限りです。本好きの方が好みそうな本から、部数が限られている個人が発行したリトルプレス、子どもの好きなコロコロコミックや絵本など、本は硬軟取り揃えておりますので、ぜひ一度お運びくださいませ。
Q2.今の仕事をするきっかけとなった事柄や本を教えてください
昔から自分の店をもとうと考えていたわけではなく、気がついたらそうした流れのなかにいました。そんな時に思い出したのが、須賀敦子『コルシア書店の仲間たち』。本を中心として、読む人書く人が行き交うコルシア書店の姿に、こんな店にしたいと思いました。
お店(出版社)を利用される方へのメッセージ
ゆっくり静かに時間をすごしていただき、自分らしい一冊を見つけてください。
あんず文庫
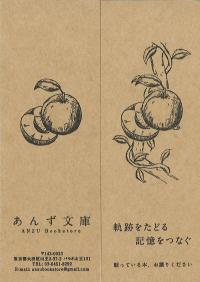
お店のご紹介
かつて馬込文士村があった山王と馬込の間に位置している古本屋です。
小説や詩集といった文学を中心に、思想哲学や歴史、エッセイやノンフィクション、絵本など他ジャンルの本を揃えております。
また、多くはないものの新本や馬込文士村関連の本(一部は閲覧用)もございます。
話し言葉にすくわれることも多々ございましたので、店の奥では珈琲やお酒をお楽しみ頂けるカウンターも設置しております。
Q1.おすすめの1冊を教えてください
『独り居の日記』メイ・サートン著/武田尚子訳/みすず書房刊
詩人である著者による58歳のときの1年間日記。作品や自身への世間の評価に苦しみ、寂しさや怒りを引き摺って、知らない片田舎での生活を綴っています。 揺れ動く感情をありのまま記したと思える言葉や、冷静な内省を経た箴言のような言葉を織りまぜながら、生きてゆくなかで生じる懊悩を孤独という情況を通じて思索してゆく一冊です。
ひとりの詩人が語り、望み、置かれにいった孤独は、ひとりの人間のそれであり、私たちのそれでもあると思えます。特にこの世情の中、すくわれる方も少なくない作品なのではと思い、推しました。
Q2.今の仕事をするきっかけとなった事柄や本を教えてください
新卒の会社を退職後、露頭に迷いながら国内外をふらふらしていました。その土地土地で出会った方々やお店、その皆さまの生活と関わってゆく中で、何かしらの形で今までずっとそばにいた本というものを店を通じて渡すこと。この生き方なら全力で頑張れるし、果てに何があっても後悔はないはずと信じたことがきっかけです。
この地(大森)で開けるきっかけになった本は家の棚にたまたま差していた『愛の詩集―室生犀星詩集』(角川文庫)と、青森の「古書らせん堂」さんで出会った『馬込の家』(伊藤人譽著/亀鳴屋刊)です。
古本屋を開けることを後押しして下さった本は、『本屋になりたい―この島の本を売る』(宇田智子著/筑摩書房刊)です。
お店(出版社)を利用される方へのメッセージ
どうか、ゆっくりなさって下されば、それ以上のことはございません。
棚の本で偶然出会う書き言葉、カウンターでのやりとりで思いがけずこぼれる話し言葉。
わずかでもそれらが皆さまの休息となればという気持ちで、日日開けております。
お気が向きましたら、ぜひ「日常のすきま」へいらして下さいね。
suiran

お店のご紹介
群馬県を拠点に古本の選書を主な活動としています。suiranの実店舗はなく、飲食店や美容室などに古本を卸しています。そこで読みたい、そこで出会いたい本を店のご主人に贈る気持ちで選書します。
月に一度、地元のFM局で本を紹介するなど、本の新旧や活動する媒体に縛られることなく、本の魅力をお届けしようと心がけています。
suiranはローマ字読みのまま「すいらん」と読みます。緑の山並みを意味する「翠巒」から。地元群馬県の風景です。
Q1.おすすめの1冊を教えてください
『よるのおと』 たむらしげる 偕成社
ある夜、少年がおじいちゃんの家へ訪ねるまでのほんの数秒間を描いた絵本。
玄関へと続く道沿いには大きな池があり、シカが水を飲んでいます。水の中をゆうゆうと泳ぐコイ。水面に浮かぶハスの葉の上にはカエルが。星空を背景にしてホタルが舞い、向こうのほうを汽車が走っています。
今、こうして過ごしている時間にもすぐそばでは数知れない動植物の営みが存在している。そんな自然の豊かさを視覚と音で味わえる傑作です。夜の青色も心に残ります。
Q2.今の仕事をするきっかけとなった事柄や本を教えてください
保育園の卒園文集に書いた将来の夢が「本屋」でした。
本をたくさん読む子どもではありませんでしたが、「本のある場所」がずっと好きでした。高校卒業後、たくさんの本屋が点在する京都に進学し、世の中にはユニークな本屋があることを知ることができました。大学生活最後の卒業制作では理想の書店を設計するほど本屋に夢中になっていました。
気がつけばあのときに書いた将来の夢を本気で叶えてみたくなりました。
お店(出版社)を利用される方へのメッセージ
お客様にはいつも「無理に読まなくていいですよ」と伝えています。だから買ってくださった本の感想をこちらから聞くことはありません。「読む機会を買う」くらいの気持ちがちょうどよさそうです。
本を手に取る。手に入れる。持ち歩く。近くに置く。眺める。触ってみる。本の“読む以外の楽しみ”も知っていただけると、本のある生活をより気軽に味わっていただけると思います。我が家なんてちょっとお見せできないほど読んでいない本(いつか読むかもしれない本)であふれていますので、どうか安心して本をお買い求めください。
タバネルブックス

お店のご紹介
東京の池上線の石川台駅にある小さな本屋です。ジャンルは主に洋書絵本、アート本を中心に小説やコミックなども取り扱っています。洋書絵本は特にチェコの絵本が多く、古書だけでなく新しい出版社からも本を取り入れて紹介しています。
Q1.おすすめの1冊を教えてください
「THIS IS PRAGUE」
出版社:Baobab(バオバブ)
国:チェコ
チェコのイラストレーターであるミロスラフ・サセックの海外ガイドブック絵本This is...シリーズのオマージュとして出版されたチェコの都市プラハのトリビュートガイドブック。本書はサセックの姪であるオルガ・チェルナによって作成さました。コラージュを使った手法が多くプラハのカフェ・街並み・鉄道・人々がユニークに表現されていて豪華な1冊となっています。
Q2.今の仕事をするきっかけとなった事柄や本を教えてください
もともとは大学でブックデザインの仕事を学ぼうと思っていたところブックデザインの授業自体がなくなってしまい、どうしようか迷っていました。本に携わる仕事には就きたいと考えていたのと、幼い頃から本屋という空間が好きだったので、そこから本屋をやってみようと思い今に至ります。
お店(出版社)を利用される方へのメッセージ
洋書絵本という少し珍しいジャンルですが、大人向け子供向けなど特に隔てなく集めており本の紙質や作り、そして内容などもなるべく丁寧に紹介しています。普段洋書の絵本などに触れる機会がない方も、もともとお好きな方もぜひ一度ご覧いただけたら嬉しいです。
ひとやすみ書店

お店のご紹介
アパートの一室にある書店です。喫茶(コーヒー、ビールなど)を併設しています。
2021年の4月で10周年でした。
置いている本ですが、エッセイ、詩集が多めです。
Q1.おすすめの1冊を教えてください
夏葉社の裏レーベル「岬書店」発行の『のどがかわいた』(大阿久佳乃)です。
圧倒されるほど、真摯な文章です。
何度も読み返しています。
Q2.今の仕事をするきっかけとなった事柄や本を教えてください
大学を中退した後、すすむべき道が定まらず、よく書店に足を運んでいました。
本の中に何かヒントがないかと血眼になって読んでいたように思います。
次第に本そのものが好きになり、自分で本屋さんをやりたいなと思いはじめました。
お店(出版社)を利用される方へのメッセージ
ここ一年ぐらい考えていたのは、自店を”気軽に入れる店ではなく、気軽に出ていける店”にしたいということでした。小さい書店で、どうしたって店員と顔を合わせることになりますから、お客さんが、気遣いや、「何も買わずに出るのは気まずいな」という思いから本を買っていただくこともなくはないと思うのですが、それは本意ではありません。気軽に店を後にしていただきたいと思っています。
野崎書林

お店のご紹介
東久留米駅西口のロータリーにあります。
「書店」+「GEO(ゲーム)」+「マルシェ(農産物)」が一体となったお店です。
今は、1月始まりの手帳や、カレンダーも各種揃っています。
Q1.おすすめの1冊を教えてください
「ナルニア国ものがたり」
イギリスの作家、C・S・ルイスの全7巻からなる子供向け小説シリーズです。
何年か前に映画化もしているので知っている人も多いと思います。
私が小学生の頃、学校の図書室で夢中で読んでいました。
タンスの扉を抜けた先にあるナルニア国。今デモナルニアと聞くと、ドキドキします。
Q2.今の仕事をするきっかけとなった事柄や本を教えてください
ブックセンター滝山グループで発行している「けやき新聞」はご存知でしょうか。テーマに沿った本の紹介の他、グループ店舗の求人情報や、イベント情報等が掲載されています。私はたまたま、仕事を探している時に、このけやき新聞に求人が掲載されていて応募しました。
お店(出版社)を利用される方へのメッセージ
書林では、GEO、マルシェを併設。マルシェでは、地元の新鮮野菜や加工品、地元に根づいた商品を売っています。
本店のブックセンター滝山と共通のスタンプカードもあり、400円ごとに1ポイント、25ポイントたまると100円のお値引きとなるサービスもおこなっています。本の他、文具やお野菜でもポイントがつきますので、ご来店、お待ちしております。
旅の本屋のまど

お店のご紹介
当店は「旅」をキーワードにした本屋です。本を通して「旅」を感じ、「旅」への想像をかきたてられる、そんな本屋をめざしています。「旅」に関連した様々なジャンルの雑誌や書籍を取り揃えており、他では手に入らないレアな雑誌、雑貨や「旅」に関連した古本も扱っています。
Q1.おすすめの1冊を教えてください
「深夜特急」沢木耕太郎
Q2.今の仕事をするきっかけとなった事柄や本を教えてください
大学生3年生の時にアメリカを2カ月旅行した際、ニューヨークの古書店街を訪れてふと入ったお店が旅の本を専門に扱っている本屋さんで、「旅の本だけを扱う本屋さんって面白いなあ」と思ったことがきっかけ。
お店(出版社)を利用される方へのメッセージ
旅になかなか行けないもどかしい状況が続いていますが、旅の本を通してぜひ「空想旅行」に出かけてみて下さい。
古本 水中書店

お店のご紹介
三鷹北口から歩いてすぐのところにある古本屋です。数年前に考えたキャッチコピーは「もっと本が好きになる町の古本屋」というもので、そういう店でいられるように、日々あの手、この手という感じで試行錯誤しています。詩、映画、哲学の三つのジャンルを店の柱のようなものと考えています。
Q1.おすすめの1冊を教えてください
ここ数日中に売れた本から一冊。佐々木基一の『私のチェーホフ』は入荷するたびにしげしげと眺め、しみじみよい本だな、と思います。田村義也の装丁もすごい。タイトルの「私の」もすてき。古本屋で見かけたらぜひ手に取ってみてください。
Q2.今の仕事をするきっかけとなった事柄や本を教えてください
学生時代に荻窪のささま書店、西荻窪の音羽館と出会ったのがおおきいです。古本屋はかっこよくて、とても素晴らしい仕事なのではないかと思いました。それから映画監督を目指したり、研究を志したり、会社勤めをしたりもしたのですが、常に心のどこかでは古本屋になれたらな、と考えていた気がします。
お店(出版社)を利用される方へのメッセージ
たとえば店に並べたい本だけを注文するというのではなく、たまたまお客さんからお売りいただいた本で店の棚をつくっているということからも分かるように、古本屋はそれだけで自律するものではなく、お客さんたちとの共同作業のようなもののなかに現れるものです。言うなればお客さんとの共犯関係。ぜひみなさんにも水中書店を利用していただき、その「共犯者」として楽しんでいただければと思っています。
七月堂古書部
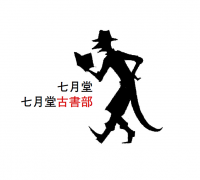
お店のご紹介
1973年に、世田谷区の梅丘という場所で、印刷会社としてスタートした「七月堂」は、そののち主に詩集を出版する出版社になりました。1990年代、小田急線の工事により、明大前へ移転。時は過ぎ、2016年、事務所に併設する本屋「七月堂古書部」を開店。
2021年初冬、約25年に渡った明大前での営業を終え、世田谷区豪徳寺に移転します。もっとずっと先まで営業していきたいという一心から決めました。
七月堂出版本はもちろん、詩歌の古本と新本、ZINEの他、絵本や文学暮らしの本、人文哲学など幅広いジャンルを少しずつとりそろえており、(少し可笑しな)街の本屋さんになりたいと思っています。
Q1.おすすめの1冊を教えてください
荒井裕樹『まとまらない言葉を生きる』(柏書房)
Q2.今の仕事をするきっかけとなった事柄や本を教えてください
七月堂は両親が創立した会社だったので、物心つく前から当たり前のように手伝っていて、そのまま就職して現在にいたります。
ですが、ただ手伝うだとか、継ぐというだけでなく、「自分の仕事」としてはどんな風にしていきたいのかと考えるようになったのは、西尾勝彦さんの詩と出会ったからです。その時手にした本は、『朝のはじまり』という素朴なちいさな輝くような詩集でした。この方の詩やことばを、少しでも遠くに届けたいと思ったことがすべてのはじまりだったのだと思います。
お店(出版社)を利用される方へのメッセージ
いつもご利用いただいているお客様も、行きたいなぁと思ってくださる方にも、SNSなどを通してご覧いただいている方にも、いつもありがたい気持ちでいっぱいです。もしご来店いただく機会がありましたら、ぼんやりしたりして、ご自分のための時間を過ごしていただけたら嬉しいです。
本屋B&B

お店のご紹介
本屋B&Bは東京・下北沢にある新刊書店です。昨年4月にBONUS TRUCKという施設に移転し、緑豊かな敷地で街の本屋として営業しています。
店内を一周すると「一番身近な世界一周旅行を体験」していただける、そんなラインナップの本が並んでいます。B&Bとは「Book&Beer」の略。ドリンク片手に本を読む、というコンセプトで本を買うだけではなく、ゆっくりと本と出会える場であるように、という思いで営業しています。
Q1.おすすめの1冊を教えてください
荒井裕樹さん『まとまらない言葉を生きる』(柏書房)
〈「言葉が壊れてきた」と思う。〉という一文から始まる本書。言葉は毒にも薬にもなりうる。その両面を荒井さんは今の社会に生きるものとしての視点で語り、悩み、そして言葉によって溶解していきます。荒井さんが本書で紹介する多くの障害者運動家の言葉は、その言葉が発せられた環境、状況の深刻さと、運動家たちも切実さのこもった言葉です。この言葉たちは障害者に限ったことではなく、私事として考えそして行動せよ!という力を与えてくれます。この本をきっかけに今、一人一人が他者と、社会で暮らすことについて、そして言葉を交わすことについて考えられたら、と思っています。
Q2.今の仕事をするきっかけとなった事柄や本を教えてください
新卒で勤めた会社で朝から終電まで働き続ける生活を続けていたとき、休みの日に行く本屋が何よりも自分の心を落ち着かせてくれる場所であったことがきっかけでしょうか。根っからの読書家であったわけではないですが、本のある場所には自然と惹かれました。一度まったく本と関係のない仕事をした後、やはり好きなものに囲まれ、好きなものを販売したいと思って書店員になり、今に至ります。
お店(出版社)を利用される方へのメッセージ
大きなお店ではありませんが、ゆったりと店内を歩きながら、今まで知らなかったけどなんとなく惹かれる本、ちょうど気になっていた事柄についての本、ずっと欲しかった本など、その時この場所で出会う偶然の一冊を手にとっていただきたいです。
本来であればドリンク片手に本を読む、という場でありますが現在はコロナウイルスの影響で店内での飲食はお休みしています。本に関する様々なイベントも開催しておりますので、ぜひチェックしてみてください!
サウダージ・ブックス

お店のご紹介
知恵をひろい、歌をおくる。波のページに耳をすませる。本の向こう側にひろがる、あこがれの風景へ。サウダージ・ブックスは「旅」と「詩」と「野の教え」をテーマにする出版レーベルです。
Q1.おすすめの1冊を教えてください
温又柔『真ん中の子どもたち』(集英社)
台湾人の母、日本人の父のもとに生まれ、東京で育った大学生の主人公・琴子(ミーミー)が、中国の上海に語学留学する。台湾、日本、中国。国や民族のはざまで生き、迷い、悩む若者たちの人生が異郷で交差する。どの「普通」にも収まらない琴子ら「真ん中の子ども」たち。自分だけの言葉、自分たちだけの言葉を探す主人公たちの旅を描いた青春小説です。
Q2.今の仕事をするきっかけとなった事柄や本を教えてください
20代の頃、ブラジルに3年間滞在した体験によって、自分の世界観は大きく変わりました。ブラジルは多民族国家。先住民インディオ、ポルトガルなどヨーロッパからの植民者、アフリカ人、日本を含むさまざまな国出身の移民たちによって歴史的につくられてきた国です。いろいろな文化的ルーツをもつ人びとが混じり合って暮らす「多様性」、遠い道のりを旅してきたよそ者を大らかに受け入れる「寛容性」を日々の生活の中で学びました。このすばらしい学びをひとりでも多くの人に伝えたい、というのが本作りの原点です。ひるがえって、いまの日本社会に「多様性」や「寛容性」は足りているでしょうか?
未知の世界を知ること、そして自分を変えること。よりよい社会のあり方を想像すること。文学を読むことも、そのためのひとつの出発点になります。旅の境涯を生きる人間の物語を通じて、真の「多様性」とは何か、真の「寛容性」とは何かを深く問いかける2冊の小説、宮内勝典『ぼくは始祖鳥になりたい』(集英社文庫)と李良枝『由熙』(講談社文芸文庫)もおすすめします。
共和国ANNEX

お店のご紹介
本当は本を売る本屋さんではなく、本を作ることだけを仕事にしている「共和国」という出版社です。東久留米に会社を作って、8年目になりました。社員はいません。
なので、実際には自分で本を売る機会はそんなにないのですが、通信販売もやっているし、たまにこういうイベントやブックフェアでは、自分で作った本を自分で本を売ることがあります。
Q1.おすすめの1冊を教えてください
藤原辰史『食べること考えること』(共和国)。いちばん最初に出版した本です。
たとえば、「私たちが日常的に口にしている食べ物は、単なる動植物の死骸なんだろうか」といった素朴な疑問から、人間が生きるうえで不可欠な「食べること」という行為について、いろいろ考えてみるための1冊です。
Q2.今の仕事をするきっかけとなった事柄や本を教えてください
藤原辰史『食べること考えること』(共和国)。いちばん最初に出版した本です。
たとえば、「私たちが日常的に口にしている食べ物は、単なる動植物の死骸なんだろうか」といった素朴な疑問から、人間が生きるうえで不可欠な「食べること」という行為について、いろいろ考えてみるための1冊です。
お店(出版社)を利用される方へのメッセージ
なんか難しそうな本ばかり出していると思われそうですが、小説や詩集、コミック、食についてなど、けっこういろんなジャンルの本を出しています。本にとっては、装釘(デザイン)も重要です。ぜひいちど、実際に手に取ってみてください。
古本 一角文庫

お店のご紹介
イベント出展を中心に営業しています。個性的な古本屋が参加する本と紙モノのイベント「TOKYO BOOK PARK」では共同運営を務め、各地パルコなど主に都内の商業施設やイベントスペースで古本市を展開しています。上井草のコーヒースタンド「slope」はじめ他業種のお店に間借りして古本棚を設置する出張販売も複数。所属する古書組合が運営する通販サイト「日本の古本屋」などでのネット販売も行っています。
Q1.おすすめの1冊を教えてください
一ノ関圭「茶箱広重」
寡作の漫画家ですが、画力は圧倒的。東海道五十三次で知られる歌川広重でなく、その跡を継いだ浮世絵師・二代目広重の葛藤と彼にまつわるさまざまな情念に着想を得たストーリーも抜群です。完全に個人的な趣味で万人にオススメということもないのですが。
Q2.今の仕事をするきっかけとなった事柄や本を教えてください
組織で働くより個人事業主が自分に向いていているのではないかと考えていた頃に古本屋という存在を思い出し、実体のあるものを売って生活するシンプルさ、情報や知恵や知識を扱いながら肉体労働でもある職業としてのバランスに他にはない魅力を感じて。
お店(出版社)を利用される方へのメッセージ
一角文庫という屋号は「氷山の一角」「街の一角」に由来しています。本の数は無数ですが、心になじむものは人それぞれだろうと考えています。一軒の古本屋に扱える量も当然限られます。どこかの街の一角で氷山の一角を売っている当店の棚を偶然ご覧になったお客様が、たまたまお好みの本を見つけてお買い上げいただくなんてことがあればそれ以上の喜びはありません。
このページに関するお問い合わせ
教育部 図書館
〒203-0054 東京都東久留米市中央町2-6-23
電話:042-475-4646 ファクス:042-475-6631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
